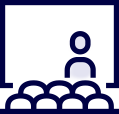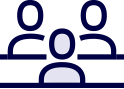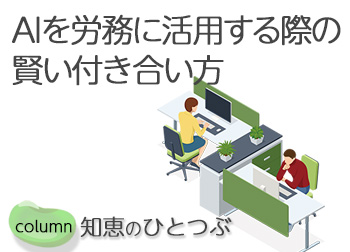時代の先を見据えて。今、経営に新しい風を!

- 主な事業内容:
- 既存建築物の調査診断、改修、機能強化工事の企画、設計施工
- 本社所在地:
- 東京都千代田区
- 創業:
- 1981年
- 従業員数:
- 16名
「大野が入社してきた当初は、こいつ、大丈夫かな?と思いましたよ。やんちゃなタイプでしたから」
「若かったですからね。そういう原さんこそ、現場では厳しい先輩でした。よく怒られたし」
「あのときは、若くてバリバリやっていたから」
およそ26年前、42歳の先輩・22歳の後輩として現場で汗を流していたが、今では68歳の会長と48歳の社長の関係になり、会社の歴史を紡いでいる。
1981年創業の株式会社日本技研は、オフィスビルや商業施設、マンション、公共施設といった建物のリニューアル・改修工事を手がける。社員数は16名と少数精鋭で、お互いが皆、顔のわかる関係性だ。だからこそ、チームワークを発揮して各現場で成果を収めて、顧客からの信頼を築き上げてきたのだ。
原敏昭会長は同社の4代目で、2015年に社長となった。20年ほど現場一筋で勤めてきたが、当時社員の中で最年長かつポジションが上だったこともあって、次期トップに選ばれたという。
「経営に関してまったくの素人でしたから、大それた経営哲学などはありません。ただ社員が安心して仕事に打ち込め、幸せに暮らせること。そんな会社であり続けなくてはと思ってやってきました」
古い価値観を払拭し、若い世代が率いる組織へ
これまで工事を請け負ってきた取引先との関係性も良好で需要も多く、売上は順調に推移。無借金経営を維持している。そんな好調のタイミングで、2024年に行った社長交代には、原会長のこんな想いがあった。

取締役会長
原 敏昭
「法律や業界を取り巻く環境などが大きく変わり始めている中で、このままでは当社のような小さな会社は生き残りが難しいだろうと考えました。例えば、働き方改革。この業界は土日や夜間の仕事もあって、かつては月に100時間残業するのが当たり前でした。当時に比べればだいぶ改善されたものの、それでも働き方の改善が遅れていると思います。変えなければいけないとわかりつつも、私はやる気や根性で働いてきた世代で、頭の片隅に昔の価値観がこびりついている。それが会社の変革を邪魔して、老害になってしまうのではないか。そう思い、意識が高く能力のある若い世代に継承するなら今だろうと判断しました」
68歳であれば、まだまだ経営者として会社を率いていける年齢であるが、「会社にとってベストな選択を」と社長交代へ踏み切ったわけだ。5代目に大野将史社長を指名した理由を、原会長はこう話す。
「彼が一番会社に対する問題意識を持っていて、それを解決しようとする意志も強かった。社内にはほかに年長で業界の経験や知見が豊富な者もいますが、総合的に考えたら大野しかいないだろうと思いました」
大野社長もまた、現場で長く活躍してきた人物。ただここ数年は営業をメインで任され、現場からは離れつつあったという。そうした環境変化の中で、会社のことを深く考えるようになったと同氏は話す。
「もし自分が上に立ったらこうしたい、ああすればもっと良くなるのではといったイメージが浮かんでくるようになりました」
会社を仕切る立場へと少しずつ意識が変わっていったのだ。「もしかしたら、そういうふうに仕組まれたのかな?」と笑う大野社長に、原会長は「実は狙っていた」と真相を打ち明ける。次の経営者候補として、あえてじっくりと会社のことを考える環境に置いたのだった。
ゆえに、原会長に社長を任せたいと言われた際、大野社長は冷静に受け止めることができたと振り返る。そして、イメージしていた組織改革を粛々と進めていくこととなる。
業界の“当たり前”を打破。人材獲得と育成にも注力
大野社長が温めていた改革プランは、大きく2つ。業務の効率化と人材の採用・育成だ。前者では、DXによる、脱アナログな組織体制を目指している。
「安全管理に関するものなど、現場関連の書類はいまだに紙へ手書きするスタイルが主流。社内でも経理処理などの事務手続きは、紙にハンコを押すやり方でした。そういった一つひとつの業務について、DXを進めました」
これについて原会長は、バトンタッチの意義を強調する。
「まさに私は手書きで育った世代ですから、それをデジタルに変えていくのは荷が重すぎる。彼ならば、うまくやってくれると思っていました」

代表取締役社長
大野 将史
これまでとやり方が変わったことに、現場からは戸惑いの声もあがった。しかし、大野社長は毅然と前進の道を歩んだという。
「新しいものに対して抵抗感があるのは仕方ない。今後、若手を採用するにあたっても、アナログ式を続けていくわけにはいきません」
業務を効率化できれば、残業時間を減らしたり、新規で受注できる案件が増えたりとメリットは大きい。
また、どの業界でも課題である人材不足についても、工夫を重ねて対策している。例えば、ホームページのリニューアルやSEO対策、求人資料の見直し。多くの企業が新卒の初任給を上げているのにならい、同社の魅力をしっかりとアピールできるように表記の仕方などを変えた。少しずつ成果が出て、新たなルートでエントリーしてくる求人者も増えてきたという。
加えて今後、力を入れたいと考えているのは、人材育成の分野だ。少数精鋭で業務を動かしている状況下で、なかなか手取り足取り新人を教える時間が取れない。その解決策を模索している。
「入社した人が自ら学べる仕組みづくりを検討しています。これまで先輩や上司が座学で教えていた基礎知識は、建設業に特化したセミナーやオンライン学習で習得できるようにするのも手でしょう。もちろん、本人がどれだけ学ぼうとするかにもよりますが、モチベーションアップや悩み相談といった人間的なフォローが必要な部分を、先輩や上司に担ってもらえるようにしたいです」
幸い近ごろの若手は、オンライン学習や生成AIなどを使って自分で調べることに慣れている。便利なツールを活用するのは、むしろ理にかなっているだろう。
先代が築いたものを維持。真摯に現場と向き合う
事業承継に向け準備したことについて尋ねると、大野社長はこう語る。
「特にないですね。社長になったら会社をこう変えたいとずっと考えていたので。ただ、いざ社長にと決まったときに、責任の重さを感じたことは覚えています」
どんなに新しい建物も、年月が経てば手を入れなければならない。昨今、あちこちで街の再開発が行われているが、そこで建てたものも定期的に修繕が必要だ。そうした意味で、日本技研が手がけている事業は順調で、短中期的にも安泰だろう。とはいえ、長期的に仕事が保証されているかはわからない。
「正直、10年、20年と先を見たときに、どうなっていくのだろうという漠然とした不安はあります。今、私は48歳で、年齢的にあと20年は社長を続けられるでしょう。それがプレッシャーでもありますね」

(写真左)内装改修工事の天井組立作業。協力業者に指示を出し出来栄えを確認しながら、工程を進める。
(写真中央)千代田区神田淡路町にある本社屋の外観。JR御茶ノ水駅からアクセスがよく、現場移動もしやすい。
(写真右)耐震補強工事の風景。建物の柱梁にコンクリートや鉄骨ブレースなどによる補強を行い、安全性を向上させる。
さまざまな観点から組織改革を進めており、会社をより良くすることに力を注いでいる同社。しかし、新規事業の創出や、会社規模を極端に大きくしようとは考えていないと大野社長は語る。
「身の丈に合わないことに手を出して、足をすくわれるようなことがあっては、元も子もありませんから」
あくまでも、これまで先代たちが築き上げてきた会社を安定的に維持していく。それが自身のミッションであると考えているのだ。同氏は、それを“枝葉を広げるのではなく、幹を太くするイメージ”と表現する。
誠実に、堅実に、一つひとつの現場と向き合っていく。これは、原会長が願っていることでもある。
「これまで通り、社員が安心して仕事に打ち込める会社、取引先に信頼される会社であり続けることに、重きを置いてほしい。そのためにはもちろん、いろいろな改革が必要でしょう。ただ、そのスピードが速すぎて付いてこられない社員が出ないように、意識してほしいですね」
直近の悩みとして、大野社長は「なかなか現場へ足を運べていない」と心情を吐露する。社員一人ひとりの顔がわかるからこそ、社長自ら話をする機会を設けて、風通しの良い組織づくりをしたい。会社の規模を極端に大きくするつもりがないのも、それが理由だと語る。
「20~25人なら各人を見られるけれど、30人以上になると今までのコミュニケーションは難しいでしょう」
現場を直接見ることに関して、今は原会長が役割をカバーしている。建設現場では安全パトロールが必須業務だが、会長自ら現場を見回り、指導をしているのだという。
「もういい年齢ですから、できたら足場なんて登りたくないですよ。でも、大野も他のメンバーもみんな忙しいから、仕方ない」
それに対して大野社長は、「いい運動になるじゃないですか」と冗談交じりで返答する。
原会長は70歳での引退を考えているというが、それまでは「彼が自由に采配を振れる環境づくりをするのが私の仕事」と、大野社長を陰ながらサポートするつもりだ。
「何かあれば助言するつもりですが、今のところ静観していて問題ないですし、この先も大丈夫でしょう」
やんちゃだった後輩が、頼もしい社長に。厳しかった先輩が、穏やかに後輩を支える会長に。より良い会社の変革には、会社を率いる人物の“人としてのより良い変化”が欠かせない。日本技研の承継は、それを教えてくれる。

(写真左上)原会長と大野社長の就任祝賀会。全社員が参加し、2人にはお祝いの花束が
贈られた。(写真左下)創業から数年後に行った社員旅行。和気あいあいとしたアット
ホームな同社の雰囲気はこの頃から変わらない。(写真右)2024年に開催したバーベキュ
ーイベントは、社員の家族も参加し大盛況。社員間の交流を一層深めることができた。
機関誌そだとう223号記事から転載