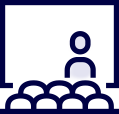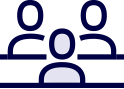ビッグイベントの前と後。日本経済はどう変わるのか
1964年の東京オリンピックで成功を収めてからおよそ半世紀。今回の「スポーツの祭典」は、来年に開催されることが発表された。
この機会を、企業経営者はどのように捉えるべきか考察していく‥‥。
望月
本日は、嶋田さんと共に、いよいよ東京で実施される、オリンピック・パラリンピック(以下、2020年五輪)が日本経済にどのような影響を与えるのか、また、私たちはこの一大イベントをどのような契機ととらえるべきか語り合っていきたいと思います。よろしくお願いします。
嶋田
よろしくお願いします。
望月
さっそくですが、2020年五輪について語るにあたり、まずは1964年に開催された東京五輪が日本の経済や産業にどのような影響を及ぼしたのかを振り返りたいと思います。
嶋田
1964年大会について語る際、よく話題に上るのが新幹線や高速道路といった国策によるインフラの整備・拡充についてです。しかし、大会の成功により大きく貢献したのは、民間企業の努力による隘路の克服だと考えています。
望月
隘路ですか?
嶋田
はい。当時の日本は世界の人々が一堂に会するような巨大イベントを開催した経験がなく、五輪運営のノウハウなど持ち合わせていませんでした。特に大きな課題だったのが、「警備能力」「選手村の飲食供給能力」「多言語対応」「コンピュータ活用」です。
このうち警備に関しては、1962年に設立された日本初の民間警備会社に発注することで切り抜けます。この後、民間警備は東京五輪での経験を活かし、70年大阪万博、72年札幌冬季五輪などで実績を積み重ねることで一つの産業へと成長していきました。
一方、残り三つに関しては、共通の根深い問題がありました。それが、“職人的属人性”です。その説明をする前に思い起こしていただきたいのですが、望月さんが子供の頃、外食といえば、どのような風景をイメージしていましたか?
望月
小学生の頃は近所にお蕎麦屋さんや中華料理店、大衆食堂がぽつぽつある程度で、たまにデパートの食堂へ行くぐらいでしたかね。
嶋田
おっしゃるとおり、ファミリーレストランのような外食チェーン店はなかったはずです。理由は、個々の料理人がレシピや調理技術を他人には教えず、技術の伝承も「見て盗め」という職人気質が色濃かったから。また、食材の仕入れから調理、お客様への提供まで個店のみで完結するのが当たり前だったため、大量仕入れ・大量調理を行う必要性も、そのための仕組みもありませんでした。
しかし、選手村となると毎日3食、各回1万人分以上の食事を提供しなければなりません。世界中から集まる選手の舌を満足させるため、多様な食文化に対応した膨大なメニューを用意する必要もあります。この課題を乗り越えるために、「一つの料理は1人の料理人がつくる」という、それまでの常識を変えました。日本各地から集めた料理人が、バックヤードのサプライセンターにおいて「チームで基本的な調理を行う」方式を確立したのです。
望月
そのサプライセンターが、現在のセントラルキッチンへと発展していくわけですね。
嶋田
はい。また、世界各地のレシピを身につけた料理人が、五輪後に全国各地へ散っていったことが、後のグルメブームの原点にもなっています。
職人的属人性からマニュアル化・システム化へ
望月
「多言語対応」というのは、どういうことですか?
嶋田
当時は海外旅行も制限されている時代で英語すらおぼつかない状況でしたから、そのほかの言語への対応など、非常に難しいのが現実でした。そこで、非常口のマークなど視覚記号の一つである“ピクトグラム”というものを生み出しました。デザインによって感覚的に理解できるサインをつくったのです。デザインの世界も料理人同様、職人気質で自身のデザイン手法を他人に教える文化はありませんでしたし、そもそもデザイナーという職業分野すらなく、絵描きの内職などと呼ばれていたものでしたが、ピクトグラムやシンボルマークが世界で高く評価されたことで、その後、グラフィックデザイン業界が確立されていきます。
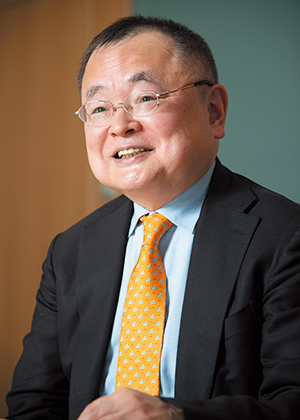
1956年、福岡県生まれ。自由が丘産能短期大学・
産業能率大学兼任教員であり、文筆家。
東京大学卒業後、エレクトロニクスメーカー、
経営コンサルティング会社などを経て、文筆家と
して独立。企業経営者など各分野のトップランナーを
数多く取材し、多数の著書や連載を執筆。
望月
グラフィックデザイン学校というものは、1964年大会以降に出てくるわけですね。
嶋田
そうだと思います。美術系の大学にグラフィックデザイン専攻ができるのも、この大会以降のことですから。
望月
「コンピュータ活用」というと、思い出すのは私が1973年に経済産業省(当時、通商産業省)へ入省して1~2年経った頃のことですね。経済計画を作成する部局にいたとき、経済成長モデルを使ったGDP予測にコンピュータを使っていました。当時はすごく大きな装置なのに、計算が遅くて、夜、帰る前に計算式をセットして結果が出るのは翌朝でした。
嶋田
1964年頃は電子計算機などと訳されていて、四則演算が速くできる高速そろばん程度の認識だったようです。しかし、1960年のスコーバレー冬季五輪で初めてコンピュータが導入されたことで、日本としても国威をかけてコンピュータ活用を進展させようと力を入れることになります。当時は、技術者が技術を抱え込んで他人が真似できないよう、わざと難しいプログラムを書くような時代でしたが、そこから脱却し、マニュアル化とシステム化を推し進めたのです。おかげで、陸上競技の着順をリアルタイムで表示するなど、競技進行面において、大きな進歩を実現することになりました。
このように、1964年大会で直面した隘路を企業の努力によって乗り越えたことで、大会は成功を収めることになります。そして、その後の日本経済や産業が発展していく一つの大きな起点になったといえるでしょう。
望月
1945年の敗戦時、日本のGDPは戦前のおよそ10分の1にまで落ち込んでいました。そこから復興に乗り出し朝鮮戦争特需などもあって、60年代から70年代前半にかけて高度成長を実現します。1964年大会はその絶頂期にあるわけで、もしかしたら高度成長の最後の仕上げを加速させたのも、この祭典だったのかもしれません。開会式でブルーインパルスが国立競技場の上空に五輪を描きましたが、その様子を多くの人がワクワクとした高揚感の中で見上げていたんだと思います。2020年五輪でも同じようなことをやるという話もありますが、どうなんでしょう。当時とは、だいぶ見え方が違うと思いますね。
嶋田
当時は「今日よりも明日の方がよくなるだろう」と多くの人が信じていましたから。
望月
そうです。給料も右肩上がりでしたし。
嶋田
だからこそ、頑張れた。その一点をとっても、1964年大会と今回では前提条件が違い過ぎると思うのです。参考にすべきは1964年大会ではなく、成熟した先進国として一つの成功の形を見せた2012年のロンドン五輪だと考えます。
ロンドン五輪を主導したのは、当時市長だったボリス・ジョンソンです。彼は、社会課題解決型五輪と謳い、貧困者が多く住む地域の再開発を進めたり、社会的弱者の雇用を促進したりしています。
望月
ロンドンでは、パラリンピックがすごく成功した印象がありますね。アスリートがしのぎを削る姿やそこから生まれる感動など、それまであまり気づくことのなかった競技としての面白さがテレビ中継からものすごく伝わってきたのです。
嶋田
それは社会的弱者に注目するというボリス・ジョンソンの方針が、パラリンピックの見せ方を変えたという部分もあるのでしょうか。
望月
見せ方だけではないと思います。これはあくまでも私見ですが、障害のある方々が目指す大会として、そして、世界という舞台で戦う最高の舞台として、パラリンピックが認められたというか。そこを目指す選手たちの気持ちが変わったのではないか、と。だから、テレビ中継越しからでも熱量が感じられ、感動を呼び起こしたのだと思います。
成熟した先進国での祭典。ロンドン大会の意味とは?

嶋田
変わったといえば、ロンドン大会を経てイギリス人自体が大きく変化したといわれていますね。非常にコンサバティブだったのがイノベーティブになった、と。そのきっかけは何だとお考えですか?
望月
ビッグイベントを成し遂げたという成功体験でしょう。あれほど盛り上がった大会を自分たちで成し遂げたという自信だと思います。当時のイギリスは、世界の中心にいた大英帝国時代とは違います。現在、世界秩序をつくっているのは超大国であり、金融においては中心を担う位置にいますが、経済全体という視点で見れば世界の中心とは言い難い。過去の栄光に比べれば輝きが薄れてきた中でのチャレンジであり、成功でしたからね。イギリス人に与えた衝撃も大きかったのだと思います。
嶋田
変わったのはイギリス人のマインドだけではありません。森記念財団都市戦略研究所が行っている世界の都市力評価では、この祭典以降8年連続でロンドンが1位を獲得しています。ロンドンは、それだけ世界から評価される都市へと変貌したことになります。
ただ、2012年の訪英外国人観光客は前年までよりも減少。ロンドン以外の地方都市への訪問も激減しています。五輪開催に伴う混雑や価格の高騰を嫌ったのでしょう。これは「クラウディング・アウト」といいますが、日本でもこの現象を懸念して、JAL(日本航空)は今夏に国内線の最大10万席を海外のマイレージ会員に無償で提供すると発表しています。ANA(全日本空輸)も大幅な割引に踏み切るようです。
望月
確かに、短期的に見れば、訪日外国人観光客は減るかもしれません。しかし、長期的視点で見れば、2020年五輪は非常に大きなチャンスになるはずです。
近年は、インバウンドを増やそうとさまざまな手を打ってきたことで着実に外国人観光客の数が増加しています。これまで数を増やすことに注力してきたことは正しかったと思いますが、そろそろ量ではなく、質を考える時にきているのではないか、と。そして、その機会として今回のスポーツの祭典が打ってつけではないかと思うのです。
嶋田
どういうことでしょうか?
望月
今までは、日本に来る外国人は銀座や京都などの名所旧跡に行ったり、買い物を楽しんだりしていました。しかし、訪れる場所が集中してしまい、非常に混雑してしまっているし、同じ場所ばかりでは飽きられるのではないか、不満が残るのではないか、日本の本当の良さを分かってもらえないのではないかといったことを懸念するむきが出てきています。だから、もっと地方にも目を向けてもらおうと、体験型のツアーを企画するなど工夫するようになってきてもいます。
しかし、今のところは、日本人が日本人の感覚で外国人に楽しんでもらおうという視点で企画したものばかり。つまり、完全なプロダクトアウトなんです。訪日する外国人もあらかじめガイドブックなどで訪れる場所を決めて、それを見るために来日している。でも、五輪目的で来る人は、そもそもの動機からして違います。
嶋田
そうですね。今回の五輪開催中に来日する外国人は、4年に一度のスポーツの祭典を見たいと思い、その開催地が日本だから来日するわけですから。
望月
そこに、外国人から見た日本の魅力を再発見するチャンスがあると思うのです。観光目的ではないからこそ、フラットな視点で日本人には想像もしていなかったような日本の魅力を見つけ出してくれるのではないか、と。
嶋田
しかも、世界のさまざまな国から訪れた人たちが、それぞれの感覚で日本の魅力を見つけてくれる……。
望月
そうです。だから、2020年五輪のために来日した外国人を対象に、帰国するときには日本の何に魅力を感じたのか、アンケートをとればいいんですよ。きっと今までにない貴重な意見がきけるはずだと思いますよ。
あるものを素直に見せて来日外国人の反応を観察する
嶋田
ここまでの話を踏まえて、中小企業は2020年の五輪という機会をどう活用すればいいとお考えですか?
望月
おもてなしをはじめとしたサービスやモノづくりなど、中小企業の人たちが提供し得るものの再発見ができるはずだと思いますね。
嶋田
確かに、やり方次第だと私も思います。最近は産業観光がずいぶん栄えてきていますよね。新潟・燕三条あたりでは金属加工のプロセスを見せたり、職人と語り合える機会を設けたりすることで人気を博していますし、醤油発祥の地である和歌山県の湯浅町では世界一の職人といわれる方が醤油づくりの過程を公開していたり。湯浅町ではインバウンドが36倍にまで増えたと聞いています。観光資源がないといっている地方であっても、ちょっとした工夫や努力でチャンスは生まれるはずです。
望月
そうですね。今は減ってきましたが、日本各地には産業の集積地がいくつも残っています。たとえば、北海道・旭川の家具などもその一つでしょう。当社の投資先でもあるカンディハウス(本社:旭川)は毎年、ドイツの家具の展示会に出展して、ヨーロッパ市場の開拓に力を入れています。木造文化の中で木を扱う技術を磨いてきた日本製の家具は、ヨーロッパの人から見ても魅力的なのでしょう。結構好評なんですよ。
嶋田
日本酒人気もあいまって、酒蔵ツーリズムというのも人気が出てきていますね。
望月
ええ。ただ、日本的なものを好きだという外国人以外も視界に入れるべきだとも思います。たとえば山梨のワインはあまり知られていませんが、飲んでもらえれば、その繊細な風味や味わいを気に入ってくれる人は必ずいるはずです。
嶋田
ウイスキーだってものすごく評価されていますね。品切れになったりしていますし。
望月
本当に。でも、今ほどの評価が得られることは期待していなかったと思うんですよ。想定できていなかったというか。だから、品切れを起こしているのでしょうし。
だから、あまりこねくり回したりせずに、今あるものを素直に見せる。そして、外国人に魅力を見出してもらうべきだと思います。
嶋田
日本のマンホールが面白いと海外で話題になったりしていますしね(笑)。それがSNSで拡散されて、いいね!がついたり。
望月
繰り返しになりますが、だから、観光しようと意気込んで来日する外国人ではなく、スポーツの祭典目的で来日しながらもフラットな視点で日本を見ることができる外国人の目というのが、とても貴重な機会になると思うのです。
制約要因を取り払い、日本地図を広い目で見る
嶋田
今回のスポーツの祭典によって懸念されていることに、東京への一極集中が加速して、地方の過疎化がますます進行するのではないか、というのがあります。
望月
それは五輪とは分けて考えるべきテーマです。地方創生は、もっと広い目で地図を見るべきだ、と。そもそも、東京という都市を考えるときは、アジアという視点で思考しないとダメなんです。それなのに、一極集中を避けようといろいろな制約を設けてしまう。だから金融センターだって他国に持っていかれてしまうんです。東京のポテンシャルを伸ばしてアジアの中で際立ったポジションを確立できれば、その効果によって日本全体が引き上げられます。だから、この二つを一つのテーブルに並べて論じるべきではありません。
嶋田
では、地方創生はどのように実現していけばいいとお考えですか?
望月
何のために地方に住むのかという理由を見つけてあげれば自然と地方に住む人は出てくるはずです。なかでも、高いポテンシャルを秘めているのは、農業ですね。北海道など広大な土地を利用して大規模農業を展開すればいいのです。日本の農作物は、海外でも人気ですから。これからの農業に不可欠といえる生産管理や原産地証明なども、日本のIT技術を活用すれば、簡単に解決できます。最近は農林水産省も輸出目標額1兆円を掲げるようになっていますし、チャンスなんですよ、今は。
あとは、成功者が出て稼げるということが分かれば、自分もやってみようと考える若者は必ず現れます。それはUターンかもしれませんし、Iターンかもしれませんが、農業に興味のある若者は決して少なくないはずです。
嶋田
つまり、制約要因を取り払って、売れる仕組みを提示してサポートさえすればいい、と。
望月
そうです。ただし、大規模農業でなければグローバル市場で競争するのは難しいので、山間の狭い農地とかではなく、北海道のように広大な土地の利活用をもっと進めていく必要があります。それぞれの産業に適した土地・場所を選択してサポートをしていくことが大切です。だから、日本地図を広い目で見るべきだとお話ししたわけです。
嶋田
聞けば聞くほど、これからは海外を強く意識したビジネスを考えなければならないわけですね。それは、中小企業であっても同様なのでしょうか?
望月
日本は信じられないくらい急激なスピードでグローバル化しています。だから、たとえ内需型の中小企業であっても、地球の裏側で起こる出来事の影響を受けるリスクを忘れてはいけません。実際、ここ数カ月だけを見ても、米イラン関係やコロナウイルスなど予測できないような出来事が発生し、その影響を受けている企業は少なくありません。だからこそ、中小企業もグローバルなリスクの感知能力を高めていかなければなりません。それはつまり、本当にグローバルな視野を身につけなければならないということ。その点でも、これまでとは一味違う外国人が大挙して訪れる今回の五輪は、貴重な機会になるはずです。
(2月7日、当社会議室にて。文中敬称略)
機関誌そだとう203号記事から転載