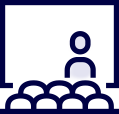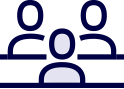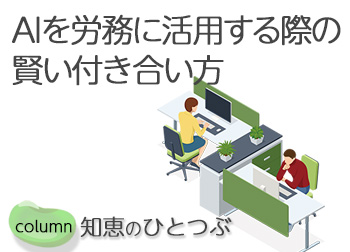AIを労務に活用する際の賢い付き合い方
多くの企業が注目しているAI(人工知能)ですが、その手軽さの裏には
大きな落とし穴が潜んでいます。今回は、そのリスクやAIと適切に向き合うための
勘所を、アクタス社会保険労務士法人の松澤隆志氏に解説していただきます。
AI活用による業務効率化は魅力的ですが、その能力を過信すると、かえって大きなリスクを招くことがあります。特に労務管理においては、AIの限界を理解しておくことが不可欠です。AIは定型的な処理を得意としますが、頻繁な法改正や、従業員一人ひとりの状況(育児休業など)に応じた例外的な処理には、柔軟に対応できない場合があります。AIの自動計算を過信した結果、保険料の徴収漏れや給与の支払いミスといった、企業の信頼を揺るがす問題に直結するリスクがあります。例えば、PCログなどからAIが労働時間を自動で判定する、勤怠データの自動チェックシステムは客観的な勤怠管理に役立ちますが、「どこからどこまでが労働時間か」という法的な解釈が求められるグレーゾーンの判断はAIには困難です。実態と乖離した勤怠管理が行われる危険性があります。
AI労務管理、その理想と現実。AI勤怠システムを過信し、労務トラブルに
最新のAI勤怠管理システムを導入し、勤怠チェックから残業代計算までを完全自動化したA社は、その典型的な失敗例です。システムは従業員の個別事情を考慮せず、PCが起動している時間を画一的に労働時間と判定。結果、多くの従業員に実態とかけ離れた残業代が支払われる事態となり、従業員からの不満が噴出しました。最終的に、勤怠データの再計算と差額の支払いに追われ、AI導入前よりも業務が煩雑になってしまいました。

一方、B社では、AIを勤怠管理の最終判断者ではなく、あくまで「補助ツール」と位置づけています。AIには、全社の勤怠データの「傾向」を分析させ、「特定の部署で残業時間が急増している」といった推論を出力させます。経営陣や人事担当者は、そのAIの分析結果を「問題発見のきっかけ」として活用し、人間が最終的な意思決定を行う体制を構築しています。AI労務管理を成功させる秘訣は、AIを「答えを出す存在」ではなく、「思考の材料を提供する存在」と捉えることです。
AIの役割は、あくまで社内データから読み取れる傾向の分析や、従業員への説明文書の草案作成といった「補助業務」に限定すべきです。AIが生成した情報は、必ず人間がダブルチェックするフローを徹底してください。また、AIが出力した情報の正誤を判断するには、使う側に正しい労働法の知識が不可欠です。AIに頼りきりになるのではなく、経営者や労務担当者自身が学習を続け、知識をアップデートしていく姿勢が求められます。
AIは、使い方次第で強力な武器にも、大きなリスクにもなり得ます。自社の状況に合わせてAIの役割を慎重に定義し、専門家の助言も活用しながら、賢く付き合っていくことが肝要です。

アクタス社会保険労務士法人
特定社会保険労務士
松澤隆志 氏
社会保険労務士として従事後、人材紹介・派遣会社、医薬品関連会社(東証プライム上場)などの人事責任者を歴任。2019年にアクタス社会保険労務士法人の社員就任。2021年に代表社員就任。社会保険労務士と人事部門双方の知見を活かし、労務管理のアドバイスを行う。
機関誌そだとう224号記事から転載