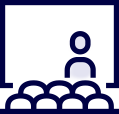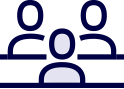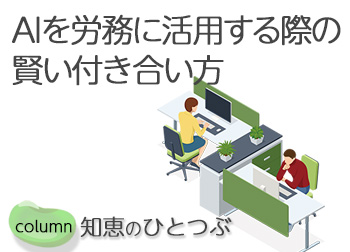~Treasure Company~
安心・安全を創造する、介護浴槽のパイオニア
- 主な事業内容:
- 介護用入浴機器、医療機器の製造・販売
- 本社所在地:
- 静岡県磐田市
- 創業:
- 1966年
- 従業員数:
- 183名

専用ストレッチャーで浴槽に連結し、寝た姿勢で入浴する「寝位入浴」、専用シャワーチェアで浴槽内まで進入し、腰掛けた姿勢で入浴する「座位入浴」、リフトの座部に腰掛け、リフトを昇降して入浴する「リフト入浴」など、介護用の入浴機器には、さまざまなバリエーションが存在する。例えば「寝位入浴」の機器だけでも、ストレッチャーの動き方や浴槽のサイズなど、さらに細かく種類が分かれ、使う人それぞれのニーズに寄り添った機器が揃っている。
静岡県磐田市に本社を構える株式会社アマノは、全国の福祉施設や医療施設から絶大な信頼を寄せられている介護用入浴機器メーカーだ。静岡県内の福祉施設では、シェア8割を誇る。代表取締役の天野哲夫氏は、「介護度に合わせて選んでいただける幅広いラインナップを揃え、お客様への提案性を高めることは非常に重要です。それが業界で生き残る鍵でしょう」と、顧客の選択肢を増やす理由について話す。
介護用入浴機器にもトレンドがある。以前はコンパクトサイズの入浴機器が重宝されたが、最近は、シャワーで入浴するタイプへのニーズが高まっているという。
「浴槽に浸かるのではなく、複数のシャワーノズルが付いたブースに入り、全身を洗いながら入浴します。介護用入浴機器には、毎回お湯を捨てるタイプと、お湯を循環させて複数回使うタイプがありますが、シャワーの場合は1回ごとに新しいお湯を使いますから、衛生面での安心感があります。また、入浴中に溺れてしまうリスクが少ないため、安全面でも選ばれています。介助者は、常に事故の危険と隣り合わせでプレッシャーを感じていますから、負担が少しでも軽くなるという点で、ニーズが増えているのだと思います」

①② 事故防止の画像処理見守り機能が付いた新製品。日本医療研究開発機構(AMED)の
令和4年度「ロボット介護機器開発等推進事業」に採択された。
③ 寝たままシャワー入浴するタイプの新製品。
今でこそ、豊富なラインナップを誇り、全国各地に処点を展開している同社だが、始まりは天野氏の父・伸一氏が試作した簡素な浴槽だった。バイクの修理工場を営みながら、父親の介護に明け暮れていた伸一氏は、自身が体感した苦労から「寝たきりの人を、安心して入浴させられる浴槽はないだろうか?」と考えた。
時を同じくして、社会福祉法人天竜厚生会から、「重度障害者を浴槽に入れるのはとても困難。何かいい方法はないだろうか?」と相談を受けたことが転機となる。伸一氏は一念発起し、介護用浴槽の開発に着手。1年もの間、試行錯誤を重ね、1965年に日本初の介護浴槽「天野式特殊浴槽」を誕生させた。
「当時は、軽トラックに浴槽を乗せて全国を売り歩いたと聞いています。私たちが暮らしていた天竜市(現在の浜松市天竜区)は、ホンダの創業者・本田宗一郎さんの出身地。父がものづくりに熱心に取り組んだのは、本田さんへの憧れがあったのかもしれませんね」と、哲夫氏は前社長である伸一氏について話す。
その後、高齢化社会への対策として国が少しずつ福祉事業を強化。法の制定をはじめとしたさまざまな取り組みに着手したことが追い風となり、軽トラック1台からスタートした事業は、軌道に乗っていった。
リーマンショックやOEMで製品を納めていた企業の撤退など、いくつかのピンチを乗り越え、創業から60年近くが経とうとする中、“アマノブランド”を前面に打ち出して、前進している。

車椅子の背が倒れるようになっていて、着替えなどがしやすい設計(写真左)。
操作パネルのわかりやすさも、介助者に寄り添った工夫の1つ(写真右)。
ふちの高さにこだわり、介助者の負担を軽減

「自社ブランドを強固にするには、開発力の充実が欠かせません」と天野氏。顧客ニーズを開発に活かすため、リアルな現場の声を吸い上げる仕組みを設けている。その1つが、業務システムの活用だ。主に顧客と直に接する営業部のスタッフが、使い勝手や要望といった顧客の話を入力して全社で共有する。大切なのは、ダイレクトな声を聞くこと。そのために、「なるべく自分の考えや感情を含まず、聞いたままの情報を書くこと」と注意を促している。
また、全国の営業所から顧客の元へメンテナンスや修理に赴くスタッフからの報告も、貴重なフィードバックだ。クレームや事故の報告も、製品の改善にとっては重要。1つ1つの声に真摯に耳を傾け、開発へつなげている。こうした丁寧にニーズを拾い上げる姿勢は、「やさしさをカタチに」というものづくりテーマの体現だ。
「入浴する利用者と介助者の両方にとって、できるだけやさしい製品をつくる。その想いが根底にあります。特に介助者の負担軽減には力を入れていて、それが当社の競合優位性だと考えています」
介助者の負担軽減につながる一番のポイントは、浴槽の「ふちの高さ」だ。高すぎると背伸びをした姿勢になり、低すぎると中腰の姿勢になって、腰への負担が大きい。介護の現場における介助者の腰痛経験は8割を超えているとの調査もあり、大きな課題なのである。
例えば、アマノの主力製品「マリンコート リモ」は、浴槽が上昇すると同時に浴槽内に備えられた担架が下降する。それによって、浴槽と担架の高さに自然な差が生まれ、グッと介助がしやすくなる。ほんの十数センチの違いだが、介助者にとっては大きな違い。これ以外にも、多くの製品が「ふちの高さ」の操作にこだわった機能を有している。

ショールームでは、実際に入浴体験も可能(実演中の天野社長)。
近年は、外部との共同研究にも積極的だ。「自社だけで取り組んだほうが、スピード感をもってできる場合もあります。けれど、外からの視点を取り入れることは社員にとって刺激になり、成長にもつながります。補助金を得て、外部の専門家などからアドバイスを受けて行う開発では、決められた予算の中でどこまでアドバイスを反映させられるかなど、葛藤しながら取り組むことも多く、それも良い経験です」
直近も、日本医療研究開発機構(AMED)の事業の1つに手を挙げ、採択された製品の開発に着手中。専門家らと意見を交わしながら、天野氏が「非常に画期的」と胸を張る新製品を、プロトタイプまで完成させている。いったい何が画期的なのか。それは、入浴中の安全性向上へのアプローチの仕方だ。
「どれだけ介助者が気をつけていても、入浴にはどうしても溺れる危険性が伴います。安全ベルトで利用者の体を固定しますが、姿勢が変わったり、体がずれたりすると、リスクが高まる。この課題を克服できないかと、5~6年ほど前から思案していたのが、画像処理を用いた見守り機能です。入浴中の利用者の顔の位置をカメラで認識し、水面に近づくと警告する仕組み。ただ、入浴中にカメラで撮影するのはプライバシー面で問題があるため、製品化には大きな壁がありました。それでも、チャレンジする意義がある。撮った画像はその都度、削除される仕組みにするなど、工夫をこらして上市まであと一歩です」
人手不足の中、介助者は1人を入浴させながら別の人の着替えを手伝ったり、風呂場の掃除をしたりせざるを得ない。安全に入浴させなければならないプレッシャーが少しでも軽くなれば、介助者の働きやすさにもつながるはずだ。
知識と意欲を向上させ、人を育てて次のステップへ
今後、高齢化率がさらに高まっていくことが予想されており、同社製品の需要も伸びが期待できる。ゆえに、人材確保と育成は大きなテーマだ。社員の成長意欲に応えるべく、外部研修やセミナーへの参加を積極的に促している他、社内での勉強会も企画。「介護セミナー」と題した全13回の講義を実施し、介護の知識を身につける。
また、営業部の新入社員はメンテナンス担当者に同行、開発部の新入社員は工場勤務など、それぞれ数カ月かけて現場を知るための研修を実施している。
「安全面の問題で実現できていませんが、本当は入浴介助の体験もしてほしい。それだけ、実際に製品が使われている現場を知ることは重要だと思っています」
海外には入浴文化がないため、介護用入浴機器については引き続き国内が主要なマーケットになるが、その分、国外のライバル出現の心配はなく、ますます同社の勢いは増していきそうだ。
「これからは、民間事業者の介護部門への進出が増えるでしょう。そこで当社がどう提案できるかが重要だと考えています。現状維持は衰退につながる。そう思っていますから、どんどん新しいものにチャレンジしていきたい。まずは画像処理見守り機能をつけた新製品を軌道に乗せ、さらに開発力を向上させて100億企業を目指したいですね」
創業者の実体験から生まれた、介助者にも利用者にもやさしい浴槽。安全と安心を何よりも大切に考える同社にしか生み出せない製品が、この先も登場し続けるはずだ。

本社の隣に構えた工場。社名を天野商事株式会社から株式会社アマノに変更したのは1989年のこと。
機関誌そだとう224号記事から転載